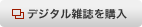この作品を最もストレートに評価したニューヨーカー誌の映画評は、「イラク戦争を最も巧みに、かつ感動的に描いた作品」「イラク戦争がもたらすいら立ちと嫌悪感にうんざりしたアメリカ人が、葛藤や罪悪感抜きに手放しで楽しめる映画」と位置付けた。
描くのは米兵の苦痛のみ
評論家のデービッド・エデルスタインも『ハート・ロッカー』の長所を指摘する際に、この矛盾をはらんだ二重性を取り上げた。「おそらく最も重要なのはその政治的メッセージ──あるいは政治的メッセージの不在だ」
確かに今は誰もが政治や政治的駆け引きにうんざりしている。だが政治を嫌うのと、政治性の欠如を歓迎することとは別物だ。葛藤を伴わない、あるいは政治性を隠したイラク戦争の映画を作ることは本当に素晴らしい快挙なのか。
かつてはこんな映画ばかりではなかった。例えば99年の『スリー・キングス』。ジョージ・クルーニーらが演じる米兵4人組は湾岸戦争直後、イラクのサダム・フセイン大統領が隠した金塊探しで一獲千金をもくろむが、その過程でシーア派の苦境にいや応なく気付かされる。アメリカにたき付けられてフセインに反旗を翻した彼らには、米軍撤退後に厳しい迫害が待ち受けていた。
この作品は手に汗握る娯楽アクションでありながら、同時に湾岸戦争終結後のイラクという舞台設定の持つ特異性にこだわろうとする努力の跡も見受けられた。
だが、昨年全米公開された「ポスト対テロ世界戦争」時代の3作品『ハート・ロッカー』『ザ・メッセンジャー』『マイ・ブラザー』は、徹頭徹尾アメリカ人兵士の傷しか描かない。ますます複雑化する世界で自分たちの苦しみしか感じられないとしたら、何とも情けない話だ。
戦時という名の心の殻に閉じ籠もったアメリカだけが世界のすべてではないことをほのめかした一握りの作品は、手に余る難問に挑んだ無謀な試みとして酷評された。
例えば星条旗が逆さに掲揚される『告発のとき』のラストシーンは、刺激が強過ぎると批判された。当局によるテロ容疑者の拉致・拷問を描いた『レンディション』は、想像力不足を指摘された。
米ケーブルテレビ局HBOが08年に制作したドラマ『ジェネレーション・キル』は、真っ向から対テロ戦争を取り上げた唯一の例外。だが、これも最後はバグダッドに侵攻する海兵隊を描いて終わる。
映画が伝えるべき物語は、ほかにいくらでもあるはずだ。だがそれ伝えるためには、この戦争をリアルにありのままに描くという発想を取り戻さなくてはならない。
具体性から逃避する傾向は映画に限った話ではない。ドン・デリーロの新作小説『ポイント・オメガ』では、イラク戦争を語るときは可能な限り曖昧な手法を使いたいと考えるアメリカ人の集団心理が物語の原動力になっている。
崩れた右派対左派の構図
『墜ちてゆく男』(邦訳・新潮社)で同時多発テロを、『リブラ 時の秤』(邦訳・文芸春秋)でジョン・F・ケネディの暗殺犯リー・ハーベイ・オズワルドを取り上げたデリーロは、現代の合理的世界観に収まり切らない人間の不合理性を追究してきた。『ポイント・オメガ』もその延長線上にある。
主人公の若い映像作家ジム・フィンリーは、かつて国防総省の顧問を務めた老学者に影のごとく付きまとう。この学者がイラク開戦に果たした役割をドキュメンタリー映画にまとめたいからだ。
だが引退した学者が暮らすモハベ砂漠に舞台が移ると、物語の流れが変わる。学者の家に転がり込んだジムはほかのこと(学者の娘など)に気を取られるようになる。
そしてある日、ジムは「レンディション」という単語を取り上げた随筆について学者に問いただそうとして行き詰まる(レンディションはブッシュ政権時代にテロ容疑者の「特例拘置引き渡し」の意味で使われた言葉。容疑者への拷問を黙認する脱法的措置だとして人権団体から非難を浴びた)。
結局、ジムは質問を思いとどまり映画製作も諦める。「真の問題はイラクでもワシントンでもなく、ここにある」と、物語の終盤でジムはつぶやく。「私たちはこの問題を置き去りにすると同時に、手に携えていく」
デリーロはいいところに目を付けた。イラク戦争に対するアメリカ人の曖昧な姿勢をはっきりと示したのは、喜ばしい変化だ。イラク関連の政治問題にあえて背を向ける『ポイント・オメガ』の登場人物を観察することで、私たちもそれが健全なことなのかどうかを自分なりに判断できるからだ。
ただし、この徹底した自己中心主義の根底にある問題をデリーロは深く掘り下げていない。代わりに文学研究者のマイケル・ベルベが、近著『レフト・アット・ウォー』で1つの答えを提示している。
ベルベはこの本で、コソボ紛争を契機に始まった「人道的軍事介入」をめぐる議論はまだ決着がついていないと説き、「伝統的な左派対右派の構図はバルカン半島では役に立たなかった」と述べる。
それ以降、外国への軍事介入をめぐる政治的立場に「ねじれ」が生まれ、この状態が現在まで続いているとベルベは指摘する。具体的には新保守主義(ネオコン)と新自由主義(ネオリベ)が手を組み、チョムスキー派(反戦主義)とブキャナン派(孤立主義)の奇妙な同盟に対抗するという構図だ。
武力行使をめぐる議論はもはや単純な左派と右派の対立ではないというベルベの説が正しければ、近年の映画や文学作品が「対テロ戦争」の政治的側面を積極的に取り上げようとしないのも無理はない。実際、リベラルなメッセージ性の強さに定評があるハリウッドも、このテーマについては挑発的な主張を一切していない。
現時点で声高な主張を展開しているのは、デリーロの小説に登場する老学者のような政治思想家だけだ。一方、ジムのような芸術家はイラクを斬新な視点から論じるという野心を捨ててしまった。
戦争映画が受けない理由
だが芸術家の存在意義は、まさにそこにある。大衆の意識を支配する漠然とした緊張感を安易になぞるのではなく、鋭い洞察とカタルシスにあふれた作品を作り出してこそ芸術家だ。
イラク戦争の映画がヒットしないのは観客の食指が動かないからというのが、世間では定説となっている。だが食指が動かないのは、今の戦争映画が「栄養」に乏しいせいかもしれない。大半の作品は「戦争は地獄」という手あかの付いたお題目を唱えているだけだ。
厄介なイデオロギーの問題には踏み込まず、戦闘をスリリングに描くことに徹した『ハート・ロッカー』は物語の背景を観客に示さないだけでなく、背景の欠落を示唆するヒントも与えてくれない。戦争サスペンスとしては見事だが、ただそれだけの映画だ。
『ハート・ロッカー』がアカデミー賞を取るかどうかはともかく、重要なテーマに取り組んだ野心的な芸術作品としてもてはやされることは間違いないだろう。観客に幻想を売り付けるのは、今も昔もハリウッドの得意技だ。
[2010年2月10日号掲載]
新着
癌の早期発見で、医療AIが専門医に勝てる理由

それでも「アラブの春」は終わっていない

安倍首相、日中「三原則」発言のくい違いと中国側が公表した発言記録

特集:サステナブルな未来へ 11の地域の挑戦
地域から地球を救う11のチャレンジと、JO1のメンバーが語る「環境のためできること」