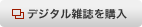だが個人的には、もうひとつ強く心に残った部分がある。開高を作家へと導いた谷沢永一を介して知り合った、牧羊子についての記述だ。
頭の回転の速い女性だった。難解な言葉を多用して形而上の理路を並べるのは天才的だ。"つまり"を連発しながら議論を展開し、熱するとしばしば机を叩きはじめる。そんな姿に同人たちは圧倒され、うやうやしく"カルメン"というあだ名を奉った。(246ページより)
当時、寿屋の研究課に勤務していた牧は、ご存じのとおり開高の伴侶となる女性だ。開高ファンの間ではあまり評判がよくなく、本書の第五章「悠々として急げ」においても、その悪妻ぶりはクローズアップされている。
なにしろ、食道がんであることを知らされないまま入院中だった開高に対し、自分がつくってきた高麗人参スープを飲もうとしなかったことから感情を爆発させ、「あんた病院にだまされてるんや。これ飲まな、がん治りゃせんで!」といい放ってしまったり(それは鬱を抱えた開高にとって、大きなダメージとなった)、佐治に対しても「サントリーのおかげで食道がんになったようなもんや!」といってのけた人だ。
しかし牧はそれ以前、つまり開高が職にあぶれていたころ、学生にして父親になってしまった夫をなんとかしようと尽力してもいる。
開高が生活難で苦しんでいるころ、(中略)寿屋に戻っていた牧が愁訴してきた。 「ミルク代が足りまへんねん。何とかなりまへんやろか」 夫の開高に、何かバイト仕事はないかというのである。(252ページより)
敬三は以前、牧が一冊の同人誌をもってきて、
「この雑誌の編集後記を書いている男と、私結婚しましてん」
とうれしそうに報告してきたことを思い出した。
「ほんならあんたの旦那に宣伝文を書いてもらおか。場合によっては、あんたとトレードしようやないか」
敬三はそんな冗談口を叩きながら、ためしにラジオCMの原稿を依頼することにした。(253ページより)
いうまでもなく、「寿屋の開高健」の誕生前夜である。つまりこの描写を見ても、牧が「縁の下の力持ち」であったことは否定できないのだ。たしかに「私が開高を養ってきた」という自我は大きすぎ、それが作家を苦しめることになったのも事実だ。それどころか、開高の死後には娘の道子が自殺し、牧本人も謎の死を遂げるのだから結末は悲しすぎる。
新着
癌の早期発見で、医療AIが専門医に勝てる理由

それでも「アラブの春」は終わっていない

安倍首相、日中「三原則」発言のくい違いと中国側が公表した発言記録